榊(さかき)は、家庭の神棚に供えられたり、神社で祭られたりと神事に関わりのある木です。
葉は青々として厚く、1㎝ほどの小さな白い花を咲かせます。

榊を自宅に植えようと思っていたのに植えてはいけないと聞いたため、どうしたらいいのかわからないという悩みはありませんか?
実は榊を植えてはいけないと言われたのは、昔の話で様々な理由がありました。
昔の人がどういった理由で、榊を植えることを断念したのか気になりませんか?
現在では、周りに迷惑をかけなければ、自宅に何の木を植えようと文句を言われることはありません。
この記事では、かつて榊を植えてはいけないと言われた理由と、他の植物と混同されやすい榊の育て方・活用方法を具体的に解説します。
目次
榊を植えてはいけない理由!現代では通用しない?

榊を植えてはいけないと言われていたのは昔と言いましたが、具体的にいつの時代かは不明です。
しかし、身分や階級の差があり、口伝で噂を話すような時代の影響が多くあります。
榊を植えてはいけない理由を解説するとともに、現在において、榊を植えるのをためらう必要がないことをお話しますね。
榊は神の木!庶民にはふさわしくない?格差社会
昔の日本では、身分の位が高い人だけが、榊を植えるのを許されていたのです。

そもそも身分って何…?
日本では、あらゆるものに神や精霊、魂が宿るとして木や岩や人形などに神を招き入れ、神を出迎える習わしがあります。
榊は神霊が憑依する神聖な木として、昔から神事に祭られることがあります。

庶民の家に神の木である榊を植えるなんて、図々しい、高慢だ!とされたのです。
そういった風潮が、やがて榊を植えてはいけないと、昔から言い伝えられるようになりました。
しかし、現代では、身分制度や庶民や貴族の線引きはありません。
誰がどこで榊を植えようと迷惑をかけなければ、他人から文句を言われることはないのです。
現代の私たちは、自分自身の言論や行動の自由を認められていますね。
榊は一本の木ですが、植えてはいけないという言い伝えから、色んな歴史に触れることができますね。
毒があると勘違い!?シキミとの違いを徹底解説
毒性の強いシキミは、榊同様お供えに使用され、葉の形も似ているためいつの間にか混同され、榊にも毒があると勘違いされていました。
シキミは、仏教では葬儀や仏花として使用される植物で、榊に非常によく似ていますが、毒があります。
ここで榊とシキミの違いを解説します。
| 種類 | 分類 | 草丈 | 置き場所 | 寒さ | 花期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榊 | ツバキ科 | 8~10m | 半日陰 | やや弱い | 夏で白色 |
| シキミ | シキミ科 | 2~5m | 半日陰 | 強い | 春で黄色 |
榊とシキミの写真をご覧ください。


パッと見ると、両方とも葉っぱが青々した緑で艶があり、違いがわかりませんね。
榊
- 葉の表は深緑色で光沢
- 葉の裏は青緑色
- 葉の長さは7~10㎝、幅は2~4㎝
- 葉の表裏ともに無毛
- 葉の中脈を軸にして表側に折れ曲がる
- 葉の先端は裏側に反り返る
シキミ
- 葉の表は濃緑色で光沢
- 葉の裏は灰緑色
- 葉の長さは4~12㎝、幅は1.5~4㎝
- 葉の表裏ともに無毛
榊はシキミより葉が大きく、葉の裏は緑色なのに対し、シキミの葉の裏は灰緑色となっています。
シキミは葉、花、果実などすべての部位にアニサチン、ネオアニサチンという毒が含まれています。
特に、果実や種子は毒性が強く口に含むと死亡する可能性があり、毒物及び劇薬取締法により劇物に指定されているのです。
| シキミの毒成分 | 中毒症状 |
|---|---|
|
|
近年でも、シキミの実を中華料理で使用されるハッカクと間違って摂取したため、けいれん等の食中毒症状を発症した事故がありました。
榊には特に毒はないのに、毒性があると勘違いされ避けられてきたのには、榊がかわいそうに思いますね。
榊には、毒性はなく子供やペットにとっても安心できる木ということがわかりましたね。
榊は病気になりやすい!?代表的な病気4選
病気が起こる可能性があることも、榊を植えてはいけないと言われた原因となっています。
榊は病気になることで、葉っぱの色が変化し、枯れることもあります。
植物に病原体は付着したわけではなく、汚れが葉や茎に付着している状態
斑点状に色がかわり、葉に穴があき、葉先から枯れる
春や秋の長い雨の時期に気温と湿度が高い状態がつづくと起こる
日光に不足が原因
木の下から進行し、全体へ広がる
高温で少雨の7~8月に発生は少なく、梅雨時期や9~10月の長雨時に増える
榊には、主に4種類の病気が起こることが知られています。
それぞれに原因が異なり、予防する対策はありますが、それは後述することにします。
見た目が暗い?純和風感ただよう榊の印象
榊の葉は深緑色で表面に光沢があり、うっそうと茂っていると暗い印象があります。

榊は、半日陰を好むため、あまり日光がよく当たる明るい場所には植えられることはありません。
そのため、より暗い印象を与えるのかもしれませんね。
榊は白い小さな花をつけますが、あまり見かけた方はいないのではないでしょうか?
花が咲くのは6月~7月の梅雨時期のため、外出頻度も少なくなります。
もともと一般家庭に植えていることが少ない木なので、見ることもないのでしょう。
意外に精錬で可憐な印象がありますね。
榊の花
恵みの雨を受け輝く pic.twitter.com/kfkHuipXQn— 石見一宮物部神社 女子神職 (@mo_nonobe) June 14, 2022
引用 Twitter

榊は神社や生垣に植えられていることが多く、葉の色も濃いことから純和風テイストな印象もあります。
近年の住宅嗜好は、和と洋の良いとこどりの傾向があります。
外観嗜好・住意識調査 <1992.9.7発表>
住宅選びで、外観を非常に重視するのは60%
最も支持が高い外観は「和洋折衷」46%
「和風」は年齢とともに高支持、逆に「洋風」は低下
引用 株式会社 住環境研究所
住環境では、和風洋風どちらの良い面を取り込んでいきたいという意識が表れていますね。
最も支持が高いのは和洋折衷ですが、年齢が上がるとともに和風テイストの支持も高くなります。
将来の和風住宅の価値を見越して、自宅に榊を植えることを考えてもいいのではないでしょうか。
榊の育て方は挿し木で日光調節が大事!方法を徹底解説

実際に榊を植えようと考えている方は、病気などのトラブルを起こさない育て方を知りたいでしょう。
ここでは榊の入手方法や育て方、豆知識をわかりやすく解説します。
榊の豆知識!大混乱!実は榊は2種類存在する?
榊には、実はもうひとつヒサカキという似た種類の木があります。
| 種類 | 分布 | 草丈 | 置き場所 | 寒さ | 花期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榊 | 西日本 | 8~10m | 半日陰 | やや弱い | 夏で白色 |
| ヒサカキ | 東日本でも可 | 10m | 半日陰 | 強い | 春で淡白黄色 |
榊は関東より西の温かな地域に生息し、一年を通して落葉しません。
榊は-9度を下回ると防寒しないと育てることはできません。
そのため関東より北の地域では、榊の代わりにヒサカキが神事の際に使用されていました。
ヒサカキは、榊より葉が小さく、葉の周りがギザギザしています。
葉っぱが小さいことから姫榊(ヒサカキ)と言われた・榊ではないため(非サカキ)と言われた等の説があります。
榊はヒサカキと区別するため、本榊や真榊と呼ばれることもあります。

これは、私が実際道の駅で撮影したもので、榊として販売されていました。
葉の周りに注目してみると、ギザギザしているため、ヒサカキですね!
榊として販売されていても、実際には榊に似たヒサカキだったということがあるので注意してみましょう。
榊の入手は切り売りがお得!簡単な挿し木法
榊はホームセンターやネットで購入できますが、在庫があまりないことや高額なことがあります。
国内で販売されている切リ売り榊の95%は、中国産で1束300~400円で販売されています。
ほとんど市場にでない5%の国産榊は、1束500円~700円となっています。
榊を手軽に手に入れたい場合には、切り売りされている榊を購入し、挿し木という育て方がいいでしょう。
切り売り榊を購入する場合には、ヒサカキか榊なのかを確認された方がいいですよ。
榊は水はけがよく、有機物が多い肥えた土を好みます。
Point
- 鉢植えにする場合は、赤玉土2:堆肥1の割合で混ぜる
- 地植えの場合は、穴を掘った土に腐葉土や堆肥を2~3割混ぜて植える
榊は寒さにやや弱いため、寒い時期に植えることは避けた方がいいでしょう。
7月~9月のように暑いがあまり雨が降らない時期は、根が張る前に枯れる恐れがあるため、避けた方がいいです。
榊を植える時期は、3月~6月か10月~11月前半が最適です。
- 榊の枝を10㎝~15㎝に切る
- 葉を数枚残し、他の葉はちぎる
- 榊の軸の茎を斜めにカット
- 水を張ったコップに榊を1日漬ける
- 翌日、苗木ポットの土に榊を挿す
土は腐葉土、赤玉土がいいがプランター用土でもOK! - 水をたっぷりとあげる
- 残した葉っぱの先1/3をカット
- 春・秋は1日1回水をたっぷりかけ、夏は太陽が落ちた後にもう1回、寒い時期は2日に1回の水やりで十分です。
半日陰で半年~1年程度経過するとしっかり根が張ります。 - 挿し木した榊を苗木ポットから出し、腐葉土と堆肥を混ぜた土に植える
- たっぷり水をあげる
こちらの挿し木方法の動画を参照してください。
引用 YouTube
榊の入手方法から、挿し木法についての理解が深まったでしょうか?
次は、榊の病気に対する予防策について解説します。
深刻な病は2つ!早期発見と対処が肝心!
榊の育て方を解説するにあたって、病気の対策は必須です。
榊には4つの病気があることはお話しましたね。
- すす病
- 白藻病
- 炭そ病
- 輪紋葉枯病

すす病と白藻病は、直接榊に病原菌が寄生しているわけではないのです!
すす病
葉や茎に現れる黒い粉のようなものがすす(煤)に似ていることから、すす病と呼ばれています。
黒い粉は、カイガラムシなどの害虫の排泄物を放置することで発生します。
害虫の排泄物は糖分が入っており、その栄養をもとにカビが発生した状態をすす病といいます。
すす病は虫の排泄物にカビが発生しているだけなので、榊本体に直接寄生していません。
榊が枯れてしまうことはありませんが、すすが表面を覆うことで光合成ができず、徐々に榊が弱ることがあります。
すす病の予防方法害虫を寄せ付けないこと
風通しが良い場所に植える
霧吹きを使って葉に水を吹きかける
すす病になった時の対策すす病のカビを落とす…水洗いしながらティッシュや歯ブラシでこする
すす病の原因の害虫を駆除する…薬剤を使用する
カイガラムシ:カイガラムシエアゾール
アブラムシ:オルトラン粒剤、アーリーセーフ
コナジラミ:ベストガード粒剤、アーリーセーフ
病気の部分を摘み取る…薬剤を使用せず、安全に除去できる
白藻病
白藻病は、半日陰を好む榊が、日光不足が原因で5~7月によく起こる病気です。
白藻病の原因は菌ではなく、藻類となります。
一日中ほとんど日光が届かない場所にあると、葉っぱに白い斑点ができます。
白藻病で、榊が枯れることはありませんが、見た目があまりよくないので、きちんと対策が必要となります。
また榊は、一日中日なたとなるような場所にあると、日光が強く当たりすぎて、日焼けをします。
葉っぱ自体はきれいですが、個体によっては、葉っぱや枝が赤く変色します。
この場合、日光が当たりすぎているので、陰をつくり日光から守ってあげる必要があるでしょう。
白藻病の予防法と対処法半日陰になるようにする…植える場所を移動、周りの木を剪定する
風通りをよくする…榊を剪定し、風通しをよくする
水やりは株の根本にあげる
炭そ病
炭そ病はカビが原因でおこる病気で、葉に黒い斑点ができ、変色して枯れていく病気です。
炭そ病は、広がりやすく放っておくと、他の葉や隣に植えている樹木にまで移っていくことがあります。
そのため、見つけたらすぐに対処することが重要となります。
炭そ病の予防法葉が密集しないよう、剪定する
水やりを葉にせず、株の根藻元にする
鉢やプランターの水はけを良くする
炭そ病になった時の対処法見つけたらすぐに、病気部分を切り取る
株全体に発生すると、株ごと処分か薬剤散布しかない
住友化学園芸 殺菌剤 GFベンレート水和剤 (炭そ病に効果があり)
輪紋葉枯病
梅雨時期や9月~10月の長雨時期に発生する、糸状菌による病気のことです。
葉に円形の褐色の病斑ができ、1㎝~3㎝になると葉枯れ、落葉します。
葉に菌が付着すると、2~3日で病斑が作られ、その後2日程度で繁殖体が作られ、一斉に病気が広がる可能性が高いのです。
周りに木や建物がなく、日光が当たり紫外線が多い場所では、病気が多数発生することがわかっています。
病斑にある菌が、雨のしぶきとともに他の場所に飛散するため、広がるのが早いです。
輪紋葉枯病の予防法一日中日当たりのよい場所におかない
半日陰になるように工夫する
風通しをよくするため、周りの木や榊を適宜剪定する。
輪紋葉枯病が発生した時病葉を見つけたら、すぐに切り除去する。
切り落とした葉や落葉にも菌が生存しているため、袋にまとめて早く処分する
日本農薬 殺菌剤 Zボルドー水和剤 500g(輪紋葉枯病に効果あり)
直接榊の葉や枝に寄生してしまっているのは、炭そ病と輪紋葉枯病なのです。
炭そ病と輪紋葉枯病は、病巣が一機に広がる傾向があり、榊そのものが枯れてしまう恐れのある病気です。
そのため早期発見、早期対処が大切ですね。
4つの病気について共通していることは、榊は日光の調節と風通しが非常に重要な木であることがわかります。
榊は半日陰で水はけがよい場所、風通しをよくすることを保つことが病気を防ぐ一番の方法です。
榊の使い方は神事がメイン!開運用や観賞用でも良し

今までは榊の育て方、病気に対する対処方法を解説してきました。
この章では、榊の使い方についてあまり知らない方向けに、昔からの使い方や意外な活用方法を解説したいと思います。
榊を神事で使うこと2例
神棚に飾る
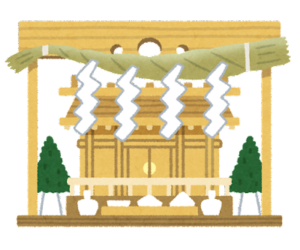
神棚は神を祀る神聖なもので、古くから榊を神木としてお供えするのは、日本独自の文化です。
自宅や会社の明るい場所の目線より高い位置に、神棚を設置していることもあるでしょう。
榊は榊立てと呼ばれる神具を用いて、水や塩とともに神棚にかざります。
榊は、イラストのように左右に一対になるようにし、その他のお供え物の端になるように配置します。
榊の葉の表が見えるように祀ると、見栄えがいいでしょう。
榊は、毎月1日と15日に新しいものに取り換えるのが一般的ですが、近年市場の95%の外国産の榊は、あまり日持ちしないものが多いです。
国産の榊は流通している5%程度ですが、圧倒的に日持ちがよく、肉厚で弾力があります。
自宅で榊を植え、自ら育てた榊を神棚に祀るのは、素敵だと思いませんか?
榊を長持ちさせる方法
榊は水をよく吸うため、榊立ての中の水がなくならないよう手入れをしてください。
気温が高くなると、水が腐りやすいため毎日水の交換が必要になります。
国産の榊だと夏場で1か月、冬場だとそれ以上長持ちします。
榊の切り口は、斜めになるように切れ味のよいハサミでカットします。
玉串
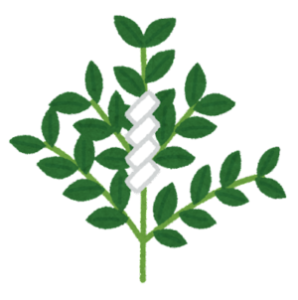
玉串は、神事において参拝者や神職が神前に捧げるもので、30㎝程度の榊に半紙で作られた四垂(しで)が付けられています。
玉串は、神前にお供えるものとして、米や酒、魚、野菜等と同様の意味があります。
玉串をささげる儀礼はどんな時?
神前に玉串をささげる儀礼を玉串奉奠(たまぐしほうてん)といいます。
例えば…こんな時に玉串奉奠を行います。
- 葬儀
- 結婚式
- お宮参り
- 七五三
- 地鎮祭
このような儀礼を経験された方もいらっしゃるでしょうか?

神棚に祀ることや玉串をささげることは、経験される機会が多いと思いませんか?
毎回榊を購入するよりも、自宅に植わった榊を活用することができれば費用面でもメリットがありますね。
ご自身で育てた榊を日本の神様に捧げることは、日本人として信心深く意味のあることでしょう。
榊の意外な活用方法!
榊で開運
榊の使い方としては、身体や心身の不調を取り除く効果があると、書籍で紹介されています。
植物の中で特に榊は、負の感情を浄化する働きがあるのです。
悪い気は植物が吸ってくれる 本
神棚以外にも、飾ると効果がありそうですね。
豪華なお花と組み合わせアレンジにする
榊は、仏花にも使える菊やユリのような豪華な花と組み合わせると、お花を素敵に引き立てます。
榊は、仏花として仏壇やお墓に飾られることもあります。
自身で育てた榊を、オリジナルのアレンジをして飾るのもいいですね。
まとめ
- 榊を植えてはいけない理由は、①身分の高い人しか植えてはいけなかった②毒があると勘違い③病気がある④和風感・暗い印象
- 榊の育て方は、切り売りされている榊を挿し木で育てるとよい
- 榊には、すす病・白藻病・炭そ病・輪紋葉枯病が発生する恐れがある
- 榊の4つの病気予防には、半日陰で水はけを良くし、風通しを良く保つことが重要
- 榊を神事で使う場合は、神棚へ飾る・玉串として捧げる場合がある
- 榊の活用は、開運や他の花とのアレンジにも可能
今回、榊を植えてはいけない理由を歴史から紐解き、現在では自由に植えていいことがわかりましたね。
榊の育て方や病気への対策についても、詳しく解説しました。
榊の活用方法は、神事・仏事はじめ多様にあります。
自身で育てた榊を、有効活用することができたらとても意味のあることですね。



